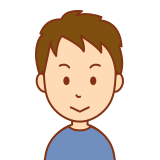
3月から就職活動が本格的にスタートすると聞いています。
でも、何をすればいいのか。。。
とっても不安です。
3月までに最低限しておいた方が良いことを教えてください。

3月からは忙しくなります。
「今から準備できること7つ」を解説します。
慌てずに就職活動がスタートできるように準備しましょう。
皆さん、こんにちは!
大学のキャリアセンターで15年間キャリアカウンセラーを務めてきたみぃです。いよいよ2026年3月卒業予定の皆さんの就職活動が本格化する時期が近づいてきました。
例年、3月の就活解禁日を前に、不安や焦りを感じている方も多いです。
などの不安を聞きます。でも、大丈夫です!
今からしっかりと準備をすれば、自信を持って就活に臨むことができます。
このブログでは、私のキャリアカウンセラーの経験を基に、
今からすべき7つの重要なステップをご紹介します。
納得できる就職活動を終えるために、今から始められる具体的な行動を見ていきましょう!
「3月就職活動解禁」とは企業の広報活動が解禁される日
大手就職サイト(マイナビやリクナビなど)で本年度の採用情報が更新され、新たに企業へのエントリーが可能になる時期を指します。
しかし、多くの就活生が
「え?今まで情報も載っていたし、インターンシップや説明会にも参加してきたのに…」と疑問に思うかもしれません。
実際、「3月情報解禁」というルールは存在するものの、すべての企業がこのルールに厳密に従っているわけではありません。
企業の中には3月以前に情報を公開し、採用活動を開始して内定を出すこともあります。反対に、4月や5月から採用活動を始める企業も存在します。
したがって、
3月の情報解禁は就職活動スケジュールの「目安」として捉えるのが適切です。
企業ごどに、採用活動の開始時期や進め方が異なります。
しかし、この時期は、多くの企業の採用情報が一斉に公開され、本格的な就職活動のスタートを告げる重要な節目となります。焦ることなく、この機会を活用して幅広い企業情報を集めましょう。
3月までにすること7つ
就職サイトに登録する
就職サイトへの登録は、就活の重要な第一歩です。
まだ登録していない方は、できるだけ早く登録しましょう。就職サイトもたくさんあります。
どのサイトに登録すればいいのか?と悩んでしまいますね。
各就職サイトにはそれぞれ特徴がありますが、どのサイトが絶対的に優れているということはありません。複数のサイトに登録することをおすすめします!
- 企業との接点を増やせる:
特定のサイトにのみに、掲載している企業もあるため - 多様な情報にアクセスできる:
サイトによって提供される情報が異なるため
ただし、複数サイトに登録する際のデメリットもあります。
- 情報管理が複雑
各サイトから様々な情報が届くため、整理が必要になります - 時間管理が複雑
複数サイトをチェックする時間が必要になります
情報管理が苦手な人や、時間に制約がある人は、使いやすいと感じたサイトに絞って登録するのも一つの方法です。
自分のペースや状況に合わせて、最適な登録方法を選びましょう。
重要なのは、積極的に情報収集を行い、自分に合った企業との出会いのチャンスを増やすことです。就職サイトを効果的に活用し、充実した就活につなげていきましょう。
気になる企業を探してみよう
インターンシップや説明会への参加は、自分の価値観や考え方、適した働き方を発見する良い機会です。サイトを見て直感的に魅力を感じた企業や、少しでも興味を持った企業には積極的にエントリーしましょう。
大手就職サイトであるマイナビやリクナビでは、3月の情報解禁を待たずに事前エントリーが可能です。1月や2月中に予約リストに登録しておけば、3月1日に自動的にエントリーできます。
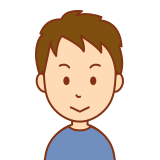
たくさんエントリーしたら、
必ず説明会や説明会に参加しないといけないのかな?

エントリーしたからといって必ずしも選考に進む必要はありません。
この段階では、幅広く可能性を探ることが重要。
大手就職サイトには掲載されていない中小企業にも目を向けることをお勧めします。
以下のような方法で探すことができます。
- 中小企業に特化した求人サイトの利用
- 就職四季報 優良・中堅企業版の活用
- 就活エージェントの利用
- 逆求人サービスの活用
幅広い視野を持って企業探しを行い、自分に最適な就職先を見つけていきましょう。
自己分析をもう一度
「また自己分析?」と思う人もいるかもしれませんが、自己分析は一度で完結するものではありません。20数年の人生経験を掘り下げるのは、簡単ではないのです。
今までの就活で、
インターンや説明会で、人事や社会人の先輩の話を聞いたときに、インターンシップのエントリーシートを書いてみたときに、ほかの就活生の話を聞いたりする中で、新たな自己発見があったはずです。
これらの新しい気づきを、ぜひ言語化し、整理してみましょう。
- 「あっ、こんな自分もいたんだ」と気づいたことをメモする
例:「人前で話すのが意外と得意だった」「細かい作業が好きだと分かった」 - 昔の経験を今の自分の目で見直してみる
例:「高校の文化祭での失敗が、今思えば大切な学びだった」 - 自分の「できること」「苦手なこと」リストを更新する
例:「パソコンスキルが上がった」「計画性が身についてきた」 - 「将来こんなふうに働きたい」と思った
例:「海外で働くことにも興味が出てきた」「起業も視野に入れたい」
この作業を通じて、自己PRや志望動機がより説得力を増し、面接での受け答えも的確になるでしょう。
自己分析は1回で終わるのでなく、継続的に取り組むことです。
就活の進行に合わせて定期的に見直すことで、自己理解が深まり、より自分に合った進路選択ができるようになります。
面倒に感じるかもしれませんが、この作業は将来の自分への投資です。丁寧に取り組むことで、自信を持って企業にアピールできる自分を見つけられるはずです。
まず初めに読んでほしい。自己分析の基本
自己分析に終わりはあるの?
履歴書・ESを書いてみる
履歴書やエントリーシート(ES)の作成は、自己分析と並行して進めることをお勧めします。
- 書いていくことで、頭の中が整理できる
書いているうちに、自分のことがよくわかってくる。モヤモヤしていた考えが、はっきりしてくる - 自分の新しい一面を発見できる
文章にすることで、気づいていなかった自分を見つけられる。「あ、こんな経験があったんだ」と振り返れる
キレイなカッコいい文章をはじめから目指すのでく、まずは気軽に書きはじめることが重要です。
- 思いついたことをそのまま書き出す
- 普段使っている言葉で構いません
- 完璧を求めず、とにかく書き始めることが重要です
- 書きづらい部分は後回しにして、書きやすいところから始めてOK
特に、「学生時代に頑張ったこと」や「自己PR」などの定番項目については、文字数を気にせず、500字以上の長文でもいいので、書いてみましょう。
単なる経験の羅列ではなく、以下の点を丁寧に書き出しましょう
- なぜその行動を取ろうと思ったのか?
- その時どのように考えたのか?
- 具体的にどう行動したのか?
- その結果、何を学んだのか?
この過程を通じて、自分自身をより深く理解できます。完成度を求めすぎず、まずは書き始めることが大切です。
後で推敲や添削を重ねることで、より洗練された内容に仕上げていけます。
摸擬面接を受ける
面接が苦手な人も多いはず。
まだ準備ができていないので、準備ができてから、面接練習(模擬面接)を受けよう!と
この時期、思っている学生さんも多いです。
早めに模擬面接を経験しておく理由は、以下の通りです。
「準備が完璧に整う日」はきません。
その日を待っていると、本命企業の本番面接が突然やってきます。
そこから、模擬面接の予約を取って、練習しても時間が足りなく、自分の本来の力が発揮できなまま、面接本番を向かることほど、悲しいことはありません。
早い時期に「自分の実力を知る」ために模擬面接を受けのも重要です。
模擬面接は、間違ってもいいんです。「失敗の場」なのです。
自分の課題を発見するため、確認するための場です。人間は失敗から学ぶことが多い。
模擬面接は本番で失敗しないために、あらかじめ失敗しておく場です。
そして、本番の面接では、客観的な意見を聞く「フィードバック」はありません。
自分の何がダメだったのか?もっと相手に伝えるにはどうしたらいいのか?
改善点を見つけにくいです。模擬面接であれば、面接を受けた後にフィードバックを受けることができます。その課題点を改善に、次に繋げることができます。
- 大学のキャリアセンター
- 地域の「新卒応援ハローワーク」
- 就職エージェント
面接が上手くなる方法
模擬面接のタイミングはいつ?何回ぐらいする?
筆記試験対策をはじめる
筆記試験対策は、他の就活準備と異なり、短期間での急激な上達は難しいものです。
しかし、コツコツと継続的に取り組むことで確実に力をつけることができます。
「早めの準備が重要」です。ESや面接と違い、時間をかけて取り組む必要があります。今からでも遅くありません。すぐに始めましょう
そして「苦手意識」を捨てましょう。
多くの学生がつまずく非言語分野ですが「文系だから数学・非言語が苦手」とあきらめないでください。
SPIなどの非言語分野は解き方のコツが分かれば解ける問題も多いです。
「効率的な学習方法を知る」非言語問題には、時間短縮のためのテクニックがあります。正攻法ではなく、効率的な解法を学びましょう。
「継続的な取り組み」が必要です。毎日30分からスタート。時間を決めて取り組みましょう。少しずつでも続けることが、確実な実力アップにつながります。
問題に慣れてくれば、本番を想定したタイムトライアルも行います。本番ではどうしても緊張してしまいます。試験当日に落ち着いて解ける状態を目指します。
最後に、多くの学生が陥りがちな誤解についてで。「苦手分野はスキップして、得意な問題に集中しよう」これは実は大きな間違いです。
なぜなら、どの試験にも簡単な問題が含まれています。
これらの基本問題は、多くの受験者が解ける「みんなができる問題」です。こうした簡単な問題を落とすのは、もったいないことです。
重要なポイントは、「試験で100点満点を取る必要はない」なので、短時間で解ける簡単な問題を確実に得点することが大切です。
苦手分野も学習し、基本的な問題は確実に解けるようにしましょう。これにより、総合的な得点力が上がり、合格への近道となります。
キャリアセンターを利用する
大学のキャリアセンターは、就活生にとって頼りになる存在です。しかし、多くの学生が利用せずにいます。
しかし、これらの心配は無用です。
キャリアセンターは常に学生の味方であり、どんな時期でも支援を提供してくれます。
- 履歴書やエントリーシートの添削
- 学校に届いている求人情報の提供
- OB・OG訪問の情報提供
- 面接練習
- インターンシップ情報の提供
- 就活に役立つセミナーや講座の開催
キャリアセンターには一般に公開されていない貴重な情報もあります。
多くの利用者が「利用して満足」と答えているという事実は、キャリアセンターの価値を裏付けています。
何をしていいかわからない時こそ、キャリアセンターに相談に行くべきです。
キャリアセンターは、就活の全段階でサポートを提供してくれる心強い味方です。活用しないのはもったいないので、ぜひ積極的に利用しましょう。
白紙の履歴書・ESでも作成をお手伝いします どう書けばいいのかわからない方でもご心配なく。一緒に考えます

大学のキャリアセンターはどんな時でも皆さんの味方です!
活用しないのはもったいない。
利用者の多くは、「利用して満足」と答えています。
何をしていいのかわからないから、キャリアセンターに相談に行ってほしい。
まとめ
このブログでは、2027年卒業予定の皆さんに向けて、就活解禁日に向けた準備のポイントを7つ紹介しました。
- 就職サイトに登録する:
複数のサイトを活用し、情報収集の幅を広げましょう。 - 気になる企業を探す:
インターンシップや説明会に積極的に参加し、自分に合う企業を見つけましょう。 - 自己分析を深める:
新たな気づきを言語化し、自己理解を深めていきましょう。 - 履歴書・ESを書く:
自己分析と並行して、文章化することで思考を整理しましょう。 - 模擬面接を受ける:
早めに実践し、課題を見つけて改善していきましょう。 - 筆記試験対策を始める:
毎日30分からコツコツと取り組み、基本問題を確実に得点できるようにしましょう。 - キャリアセンターを利用する:
どんな段階でも相談できる心強い味方です。積極的に活用しましょう。
就活は3月1日の情報解禁から本格化しますが、それまでの準備が重要です。この7つのステップを着実に進めることで、自信を持って就活に臨むことができるはずです。頑張ってください!
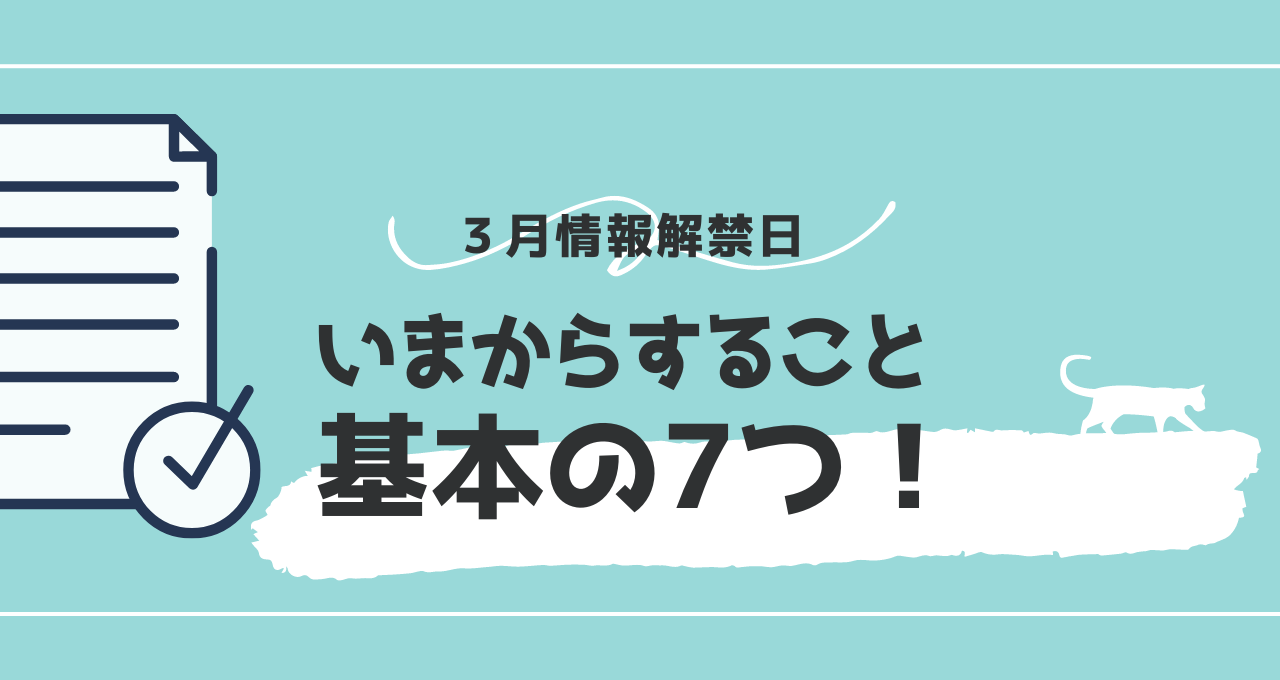
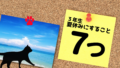

コメント